老後のお金はいくら必要?平均生活費など夫婦・独身別に紹介
老後のためにいくら準備をしておけばいいか?と悩んでいる人はとても多く、当事務所へのご相談のトップ3に入る内容です。
少子高齢化が進む中、公的年金制度はあるものの、「本当に年金だけで生活できるのか」「私たちの時には年金はもらえないのではないか」「公的年金で不足する金額はどれくらいなのか」と不安を抱えている方は多いのではないでしょうか。
さらに2019年に話題となった「老後生活費2,000万円不足問題」により、漠然とした不安がより具体的な数字として広がりました。
そこで本コラムでは、統計データをもとに、老後の生活費や年金額の実態、さらに見落としがちな税金や社会保険料など非消費支出まで含めて、夫婦二人・独身別に必要老後資金の目安を整理します。
老後の生活費はどれくらい?
老後に必要なお金を考えるには、まず「1か月の生活費」がどれくらいかかるのかを知ることが出発点です。
高齢夫婦世帯の平均生活費
総務省「家計調査」によると、65歳以上の無職夫婦世帯の1か月の消費支出は 約27〜28万円。
主な内訳は次の通りです。
| 項目 | 平均支出(月額) |
| 食費 | 約7万円 |
| 住居 | 約1.5万円 |
| 光熱・水道 | 約2万円 |
| 医療費 | 約1.5万円 |
| 交通・通信 | 約2万円 |
| 教養娯楽 | 約2万円 |
| その他 | 約10万円 |
これに対して、旅行なども行って、充実した生活を考えた場合の「ゆとりある生活」を考えた場合、月30〜35万円程度 が必要とされています
高齢単身世帯の平均生活費
独身で暮らす場合は夫婦に比べると抑えられますが、それでも月14〜16万円程度 が平均とされています。
賃貸住まいの方は住居費が上乗せされるため、20万円近くになるケースもあります。
「独身だから、夫婦二人の半分」というわけにはいきません。
「ゆとりある生活」なら 月18〜20万円 が目安と言われています。
実際の老後の生活費を考えるには?
これまで紹介した「老後の生活費」はあくまで統計データ上のものです。
ですので、実際の老後の生活費を考える場合は、あなた自身の今の生活費から老後の生活費を導き出すのが一番リアルな老後の生活費になります。
ですので、まずは今あなたが毎月、もしくは年間いくら使っているかを把握して、できれば支出科目ごとの金額も把握するとよりリアルな老後の生活費をイメージすることができるようになります
項目でいうと、代表的なものとして次のようなものがあります
・食費
・外食費
・日用雑貨費
・水道光熱費
・携帯電話などの通信費
・住居費
・娯楽費
・保険料
・趣味費
・被服費
・理美容費
・治療費
毎月かかるものもあれば、年間または不定期に必要なお金もあるでしょう
これらをなるべく正確に把握し、老後生活がスタートした時に減るか、増えるかをイメージし、どれくらい変化があるかを考えれば、非常にリアルな老後の生活費を把握することができます。
簡単に生活費を割り出すには、手取り額に対して、いくら貯金ができているかをチェックしてみましょう。
例えば月の手取りが25万円、毎月積み立てNISAを3万円していて、収支はトントンとすれば、月22万円使っていることになります。ボーナスが一回50万円で20万円のこっているとすると、年間で60万円使っていることになります。
このことから、
22万円×12か月+60万円=324万円
324万円が今使っている支出となります。
もう少しざっくり計算したい場合は年間の貯蓄額から考えてみましょう。手取り500万円、毎年貯金が150万円増えているとすれば、年間の支出は350万円ということになります。
ここから、老後には減るであろう支出の金額や増えるであろう支出を考慮した金額が年間の老後の生活費になります。
何にせよ、まずは今の生活費を把握して、そこから老後の生活費をイメージすることがとても重要だということです。

公的年金でどれくらい賄える?
次に、収入面を見てみましょう。
夫婦の年金受給額
厚生労働省によると、夫婦2人の平均的な年金受給額は 月22〜23万円。
夫が厚生年金、妻が国民年金という組み合わせが多いです。
必要生活費との差額は 毎月5万円前後の赤字。
年間にすると60万円、20年間で1,200万円不足します。
独身の年金受給額
単身世帯の場合、平均受給額は 月12〜13万円程度。
必要生活費との差額は 毎月2〜3万円。
年間30万円、20年で600万円の不足が生じます。
老後の公的年金額を確認するには「ねんきん定期便」をチェックしよう
前述の年金額はあくまで「目安」です。前述の夫婦二人の年金はあくまで、「平均的な年収の会社員の男性と専業主婦の女性の月額」でしかありませんし、独身の場合は「平均的な年収の会社員」の年金月額となります。男女ともに働き方はさまざまです。共働きの家庭もあれば、二人とも自営業の家庭もあるでしょう。
実際の公的年金の支給額は、働き方や働いている期間、収入などによっても変わってきます。
なるべく正確な年金額を把握するのに便利なのが「ねんきん定期便」です。
ねんきん定期便は、日本年金機構から毎年誕生月に送られてきます。年金の加入実績や将来の見込み額を確認することができます。
49歳までと50歳以降で内容が違う
ねんきん定期便は 49歳まで と 50歳以降 で内容が大きく変わります。
49歳までの人に送られてくる年金定期便に記載されている年金額は「これまで納めた保険料に基づく年金額の見込み」が記載されます。つまり、現時点での加入実績分だけ で計算されていて、60歳、65歳まで働いたときにもらえる金額が記載されているわけではありません。今後も働いて保険料を納め続ける分は加味されていないため、年金額は少なめに見えます。
実際、当事務所にFP相談に来られた20代の人は「年金が年間20万円しかもらえないと書いてある。年金保険料を払っていて意味があるのか」といった質問を何度も受けたことがあります。あくまで、今まで払った分に対する老後の年金額であることを理解しましょう。
50歳以降は「60歳まで同じ条件で働き続けた場合の年金見込み額」が記載されます。つまり、将来の見込みがより現実的な金額として示されます。しかし、年収の増減や60歳以降も働いた場合の年金額まではわかりません。例えば、65歳まで会社員として働くのであれば、5年間分の年金保険料を払うことで老後の年金額は増えることになります。逆に55歳で役職定年になり、年収が下がった場合は、支払う年金保険料が減ることにより、老後の年金額が減ることになります。「絶対この金額がもらえる」わけではないので、注意しましょう。
このように、50歳以降の年金定期便に記載されている情報も変化がないわけではないので、あくまで目安としてみる必要がありますが、比較的現実的な年金額と考えていいでしょう。

老後資金はいくら準備する必要があるか?
「老後2,000万円問題」のからくり
冒頭にも紹介したように、2019年の金融庁の報告書では「夫65歳・妻60歳の夫婦が30年間生きると約2,000万円不足する」と試算されました。
これは「夫婦で月27万円の支出、年金月22万円の収入」という前提に基づいたものです。
- 生活費:月27万円 → 年324万円
- 年金収入:月22万円 → 年264万円
- 年間赤字:60万円
30年間で 1,800万円 の不足。
この数字が基に国会でも論議となり、ニュースで報道されたことから「老後、公的年金だけでは2,000万円不足する」というキーワードが独り歩きしてしまいました。
実際の老後の生活費の不足額は?
住居費の違い
老後の生活費を大きく左右するのが「住居費」です。
- 持ち家で住宅ローンを完済済みの場合:固定資産税や修繕費程度で済み、月数千円〜数万円に抑えられますが、ある程度長く住んでいるとリフォームをする必要もあるため、リフォーム代金などを必要な老後資金として考えておく必要もあるでしょう。また、退職後も住宅ローンが残る場合は、年金生活になっても住宅ローンの支払いが必要になりますので、「持ち家だから老後のコストは減る」とは一概に言えません。
- 持ち家で住宅ローンが残っている場合:完済している家庭と同様に固定資産税や修繕費、リフォーム代が必要な上に、月々の住宅ローンの支払いも続くことになります。「退職金で繰上げする」という人も少なくありませんが、結局は老後のためのお金が減ることになります。年金生活になったタイミングで退職金などを原資に繰り上げ返済を行うのか、継続して払い続けるのかを考える必要があるでしょう。
- 賃貸暮らしの場合:家賃が継続的に必要になります。しかし、持ち家に比べると修繕費やリフォーム費用などは不要のため、リフォーム費用などを置いておく必要がなく、月々の支出で管理することができるのがメリットですが、住宅ローンの返済がなくなった家庭に比べれば住居費の負担がある分、月々の支出が多くなり、公的年金などの月々の収入だけで不足する場合は、貯金などから取り崩す必要があります。
医療費・介護費の差
高齢になるほど医療費や介護費の負担が増える傾向があります。
- 健康状態が良好な人:治療費も少なく、健康診断などの年間数万円程度の費用で済む。
- 持病が多い人や介護が必要になった人:医療費・介護費が年間数十万〜百万円単位になることもあります。
今は健康であっても、介護にかかる費用などは、ある程度想定しておく必要があるでしょう。
例えば、わたしの場合ですと、50代になってから、健康診断で指摘をうけるようになってきました。具体的には、緑内障や膵臓に水疱があるということから、定期的に検査を行うようになり、医療費負担が増えました。具体的には、年間で7~9万円程度です。もしかすると年齢を重ねていくとされに負担が増えることを考えれば、年間で10~20万円、月々に直すと、1~2万円程度は最低でも考えておく必要があると思っています。
趣味や娯楽への支出
老後の楽しみ方によっても不足額は変わります。趣味が読書や散歩など、お金をあまり使わないかもしれませんが、旅行、外食、習い事などに積極的な人は、月5万円以上の上乗せ支出も珍しくありません。
「どんな老後を過ごしたいか」で、不足額は変わってくることになりますので、「自分が描く老後のライフスタイル」にいくらくらいのお金がかかるか考えてみましょう。
例えば、「毎月1回はゴルフに行きたい」となれば、毎月1~2万円程度は必要になりますし、「春と秋に国内旅行」となれば、夫婦二人で年間20万円程度は必要になることもあるでしょう。
このような、月々に発生するわけではないが、1年の間に何度か出ていく支出に対しても意識を向けることが大事になります
子どもや孫への支援
自分たちの生活費だけでなく、子どもや孫への援助をするかどうかもポイントです。
結婚資金や教育費、マイホーム購入の援助。孫のお祝い事やイベント毎に対してのお祝いやプレゼントなども必要になることがあるでしょう。
こうした支援やお祝いは「生活費不足」とは別枠ですが、家計全体に影響するため実質的には不足額を押し上げる要因になりますので気になる人は必要なお金として考えておきましょう。
地域による生活費の差
地方と都市部では生活コストが異なります。
たとえば、都市部の場合、住居費やサービス利用料が高くなる反面、公共交通機関が整備されているため車の持つためのコストがかからないかもしれません。一方、地方の場合、家賃は比較的安いが、公共交通機関が整備されておらず、車が必要なため、車の維持コストが必要になることもあるでしょう。
あなたが考える老後の生活圏で必要なお金がどの程度なのかを考えることも大事です。
消費支出以外にも注意したい費用
生活費シミュレーションで忘れられがちなのが「非消費支出」です。
非消費支出とは、食費や日用品、水道光熱費や通信費(スマホ代)といった、日常生活で必要な商品やサービスを購入するのとは異なり、生活に不可欠ですが、自分の意思で支払うものではなく、収入や所有しているマイホームや車にかかる費用などです。
具体的には次のような費用になります。
税金
年金も課税対象です。働いて得た収入だけでなく、国民年金や厚生年金も収入とみなされます。公的年金等控除といって、ある一定の金額については非課税が適用されますが、それを超える部分には所得税・住民税が課税されます
企業年金、退職金、個人年金、投資収入なども課税の対象となっています。これらについても公的年金と同様にある一定の金額までは非課税となることもありますが、非課税部分を越える金額については課税がされますので、「もらえる金額=使える金額」ではないことを知っておきましょう。
社会保険料
年金やその他の収入によって負担する金額は異なりますが、次の金額程度は負担する必要があると考えておきましょう。
- 健康保険料:年金天引き、年10〜15万円
- 介護保険料:65歳から徴収、年6〜12万円
固定資産税
持ち家の場合、所有する不動産(マンションや戸建ての建物や土地)に対して固定資産税という税金を支払う必要があります。
固定資産税は不動産の価値によって異なりますが、年間10~15万円程度は必要と考えておきましょう。
実際の固定資産税額は、もし、今現在持ち家の場合、支払っている金額が持ち家を持っている限り支払う必要があると考えておきましょう。
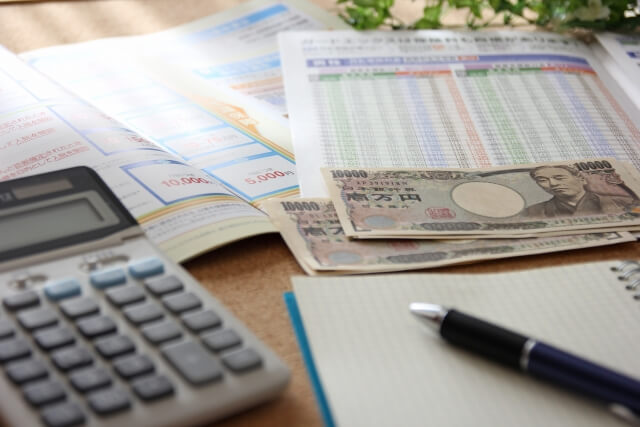
老後資金の貯め方
年齢やリスクをどれだけ取れるか(リスク許容度)などによって、選択する商品や制度は様々ですが、次のように考えて商品や制度を使ってみましょう
非課税制度を使って、効率的に増やす
- iDeCo(個人型確定拠出年金):掛け金は所得税・住民税の算定から外れることで支払う税金を減らすことができることや、利益に対して非課税となり、受け取るときも各種控除を利用することができ、効率的にお金を準備することができます。原則60歳まで引き出せないので確実に老後用の資金を準備することができます。
- NISA:利益に対しての税金が非課税になることから、効率的に増やすことが期待できます。iDeCoのように60歳まで継続する必要もありませんので、余裕資金があるときだけ投資をする、老後資金以外の目的にも柔軟に使える、といった特徴があります。
確実にお金を準備預貯金・安全資産の確保
- 預貯金:証券口座の開設なども行う必要がなく、簡単に始めることができます。いつでも引き出すことができますから、万が一の医療費などにも活用できます。
- 個人向け国債:満期まで保有すれば、元本割れがなく、安心して預けることができる資産のひとつです。1万円からでも始めることができます。
控除を活用して貯める
- 個人年金保険や終身保険:ある一定の金額まで生命保険料控除などの対象となるため、 年末調整などでの還付を受けながら、老後資金準備をすることができます。ただし、満期などまで契約を続けないと元本割れするリスクもあります。
まとめ
統計データなどでは、老後の生活費は、 夫婦で月27万円、独身で月15万円程度といわれており、年金だけでは不足し、30年間で夫婦1,800万円、独身1,000万円の赤字と言われています。
ただし「税金・社会保険料・固定資産税」など非消費支出を加えると、不足額はさらに膨らむ可能性はあり、人によって支出の大きさは異なります。
老後資金の準備を行うときには、「自分の場合はこれくらい必要」ということをこの記事を参考に考えていただければと思います。
